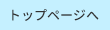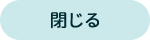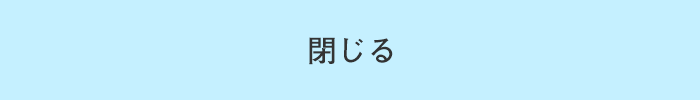予防接種とは

予防接種とは、ワクチン(病原体や毒素の力を弱めて作った薬液)を接種することで免疫力をつけ、病気に対する抵抗力をつけて発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法のことです。
赤ちゃんは、お母さんからいろいろな病気に対する免疫力をもらいますが、その免疫力は、生後8か月から12か月ごろまでに失われていきます。そのため、赤ちゃん自身が免疫力をつけなければなりません。
この、免疫力をつけるのに役立つのが予防接種です。
また、予防接種によって免疫をつけた人が多いほど感染症の流行を抑えることができるので、社会全体の感染症予防にも役立ちます。
予防接種の種類
予防接種には、法律に基づいて市町村が実施する定期接種と、接種者が希望により受ける任意接種があります。
定期接種と任意接種については、下記リンク先をご確認ください。
定期接種と任意接種について/種子島 西之表市 (nishinoomote.lg.jp)
ワクチンの種類
病原体(病気の原因となるウイルスや細菌)または菌がつくりだす毒素の力を弱めてつくった薬液のことを「ワクチン」といいます。
ワクチンには、主に次の種類があります。
生ワクチン
生きた病原体の毒性を弱めたものです。 接種すると、体の中で病原体の増殖がはじまります。
そのため、接種後は、その病気にかかったのに近い免疫をつくることができますが、発熱や発疹など、その病気にかかったときにでる症状が、軽くでることがあります。
生ワクチンでは、接種してから十分な免疫ができるまで約1か月かかります。
不活化ワクチン
病原体を殺し、毒性をなくして、免疫をつくるのに必要な成分をとりだしてつくったものです。
病原体はすでに死んでいるので、接種しても体の中で増殖しません。そのため、何回も接種して、体に記憶させることで免疫をつくっていきます。
接種した後、放置すると、少しずつ免疫が低下していきますので、免疫力を保つためには、一定の間隔で追加接種していくことが必要になります。
トキソイド
菌がつくりだす毒素をとりだし、その毒性をなくしたものです。不活化ワクチンと同じく、数回接種して免疫をつけます。
組換えタンパクワクチン
病原体のタンパク質からつくられたもので、生ワクチンや不活化ワクチンとは違い、ウイルスそのものは使用していません。
不活化ワクチンと同じように、複数回の接種が必要となります。
例:ヒトパピローマウイルス、B型肝炎、帯状疱疹ワクチン
ウイルスベクターワクチン
ウイルスの遺伝情報を、毒性・病気になる性質のないウイルスに組み込んだもので、新型コロナウイルス感染症のワクチンで初めて使われています。
例:新型コロナワクチン
メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン
ウイルスの遺伝情報の一部を使ったものです。
新型コロナウイルス感染症のワクチンで、世界で初めて実用化されました。
例:新型コロナワクチン
実施方法
予防接種の実施方法には、個別接種と集団接種の2種類があります。
個別接種
本人(または保護者)が、選択した医療機関(診療所や病院)に行って、個人で予防接種を受ける方法です。
持病など自身の状況を知るかかりつけ医を選ぶことで、安心して予防接種を受けることができるという利点があります。
集団接種
自治体(市区町村)や職場が接種会場を設置し、指定する日時・場所に集まって集団で予防接種を受ける方法です。
※現在、西之表市が実施している集団接種はありません。
定期接種について(対象者、標準的な接種期間など)
| 種類と接種回数 | 対象の年齢 | 標準的な接種期間 | |
|---|---|---|---|
| ロタウイルス | 初回2回 |
生後6週~24週に至るまで |
生後2か月~24週に至るまで |
| B型肝炎 |
初回2回 追加1回 |
生後2か月~1歳に至るまで |
生後2か月~9か月に至るまで |
| 初回3回 |
生後2か月~60か月 |
生後2か月~7か月に至るまで |
|
| 追加1回 |
初回(3回)の接種終了後60日をあけた生後12か月~15か月 |
||
| 4回 |
生後2か月~90か月 |
生後2か月~12か月 |
|
|
1期初回 (3回) |
生後2か月~90か月 |
生後2か月~12か月 |
|
| 1期追加 |
生後2か月~90か月 |
1期初回接種(3回) |
|
| ヒフ゛ | 初回3回 |
生後2か月~60か月 |
生後2か月~7か月に至るまで |
| 追加1回 |
初回(3回)接種終了後から7か月後~13か月の期間 |
||
| 回 |
生後1歳に至るまで |
生後5か月~8か月に達するまで |
|
| 1期 |
生後12か月~24か月 |
ー | |
| 2期 |
就学前1年間(5~6歳) |
ー | |
| 初回 |
生後12か月~36か月 |
生後12か月~15か月 |
|
| 追加 |
初回接種終了から6か月~12か月後 |
||
|
1期初回 (2回) |
生後6か月~90か月 |
3歳~4歳 |
|
| 1期追加 |
生後6か月~90か月 |
1期初回接種(2回)終了後1年後 4歳~5歳 |
|
| 2期 |
9歳~12歳 |
9歳~10歳 |
|
| 二種混合 | 1回 |
11歳~12歳 |
11歳(小学6年生) |
|
2回 または3回 |
小学6年生~高校1年生相当の女子 |
中学1年生女子及び中学3年生の女子 |
|
| インフルエンザ | 1回 |
65歳以上 (及び心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。) |
ー |
| 新型コロナウイルス | 1回 |
65歳以上 (及び心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。) |
ー |
| 1回 |
65歳 (及び心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。) |
65歳の誕生日から66歳の誕生日の前日まで |
|
| 帯状疱疹 |
1回 または2回 |
|
ー |
ワクチンの接種間隔
異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔

<注射生ワクチンを接種した方>
- 次回の接種が注射生ワクチンの場合は、27日以上の間隔を置く必要があります。
- 次回の接種が注射生ワクチン以外(経口生ワクチン・不活化ワクチンなど)は、接種間隔に制限はありません。
<注射生ワクチン以外(経口生ワクチン・不活化ワクチンなど)を接種した方>
- ワクチンの種類に関わらず、接種間隔に制限はありません。
ワクチンの種類
注射生ワクチン:麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン:ロタウイルスワクチン など
不活化ワクチン:ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・4種混合ワクチン・日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など
同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際の接種間隔

- 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。 くわしくは国立感染症研究所のホームページをご確認ください。
接種前・接種後の注意事項について
接種前
- 予防接種の必要性や副反応について説明する。
- 母子健康手帳、予診票をもとに問診をする。
接種後
- 接種後30分間は、急な副反応が起こることがあるので、保護者に接種会場で子どもの様子をよく観察するよう周知する。
- 接種後生ワクチンでは2週から3週間、不活化ワクチンでは24時間は副反応の出現に注意させる。
- 接種当日の入浴はさしつかえないが、接種部位をわざとこすらないようにさせる。
- 接種当日は激しい運動は避けさせる。
- 接種後は、母子保健手帳に予防接種の種類、日時、反応などを記入する。
接種を受けることができない人
- 明らかに発熱のある人(明らかな発熱とは、37.5度が目安です。)
- 重い急性疾患にかかっている人
- その日に受ける予防接種によって、接種後30分以内にひどいアレルギー反応(アナフィラキシー)が出たことがある人
- その他医師が不適当であると判断した場合
接種を受ける際に注意が必要な人
- 心臓病、じん臓病、肝臓病や血液、その他慢性の病気で治療を受けている人
- その日に受ける予防接種によって、以前2日以内に発熱、発疹(ほっしん)、じんましんなどアレルギーを思わす異常がみられた人
- 今までにけいれんを起こしたことがある人
- 今までに中耳炎や肺炎などによくかかり、免役状態を検査して異常を指摘されたことのある人
- 今までにぜん息と診断されたことがある人
- 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーがあるといわれたことがある人
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課健康増進係(保健センターすこやか)
電話番号0997-24-3233(直通)
ファックス番号0997-24-3234
メールフォームによるお問い合せ