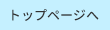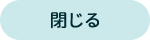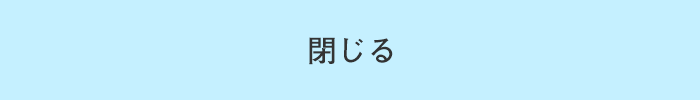38 ニガダケのある生活
新型コロナウイルス流行で、
の講師湯浅邦弘教授(大阪大学、中国古代思想史)の近著「
月刊誌の連載を単行本にした24編の一つ「
には、種子島の千ちくら座の岩屋が紹介されています。
島の時間に思いを致す5月、古田地区でニガダケ収穫の入山式があり、竹山の入り口を塩と焼酎で清め、山の恵みに感謝しました。料理法は湯がく、焼く、煮物、天ぷら、味噌汁と多彩。地域住民の生産組合が島外にも出荷し、ふるさと納税の返礼品としても人気上昇中です。
竹山の斜面歩きは健康づくりになるし、
コロナ収束に向けて「新しい生活様式」が唱えられ、時間・
の講師湯浅邦弘教授(大阪大学、中国古代思想史)の近著「
月刊誌の連載を単行本にした24編の一つ「
には、種子島の千ちくら座の岩屋が紹介されています。
島の時間に思いを致す5月、古田地区でニガダケ収穫の入山式があり、竹山の入り口を塩と焼酎で清め、山の恵みに感謝しました。料理法は湯がく、焼く、煮物、天ぷら、味噌汁と多彩。地域住民の生産組合が島外にも出荷し、ふるさと納税の返礼品としても人気上昇中です。
竹山の斜面歩きは健康づくりになるし、
コロナ収束に向けて「新しい生活様式」が唱えられ、時間・

収穫の始まったニガダケ