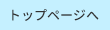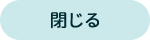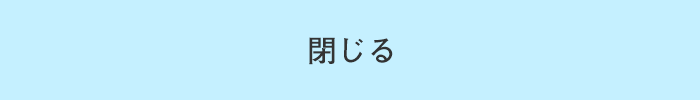37 日本一の走り新茶
番屋峯の茶畑が3月末から4月にかけて、
一斉に伸びた新芽は陽光に輝き、製茶工場には、蒸し、
番屋峯は標高250m前後と、種子島の背骨のような高台にあり、
碑文によると、初代熊毛郡長(今の熊毛支庁長)
入植当初は、サルやイノシシ、シカが棲む原生林だったそうです。
その後、全国でも優秀茶業地区と目されて視察団が訪れ、
ペットボトルが普及する近年、リーフ茶の需要低下、
一斉に伸びた新芽は陽光に輝き、製茶工場には、蒸し、
番屋峯は標高250m前後と、種子島の背骨のような高台にあり、
碑文によると、初代熊毛郡長(今の熊毛支庁長)
入植当初は、サルやイノシシ、シカが棲む原生林だったそうです。
その後、全国でも優秀茶業地区と目されて視察団が訪れ、
ペットボトルが普及する近年、リーフ茶の需要低下、

一番茶の摘み取りが進む番屋峯