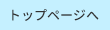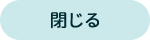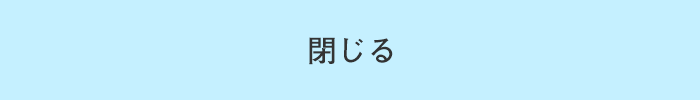知っておきたい!「保険(ほけん)・年金(ねんきん)」のいろいろ!
「病気やけがで、体が思うようにうごかなくなった」
「年をとるとともに、生活するのが大変になってきた」
「つづけていた仕事がなくなってしまった〔失業(しつぎょう)〕」
「お年寄りになったときの生活が不安だ」
このように、とつぜん今までの生活をつづけられなくなってしまう出来事がおきると、困りますよね。
しかし、こうしたことが、いつおきても、安心して生活をつづけらるようにそなえておく制度があります。それが、「保険」です。
保険には、病気・けがをしたばあいや、失業したばあいなど、さまざまな状況におうじて、それぞれに用意されています。
ここでは、市役所であつかっている「国民健康保険(こくみんけんこうほけん)」、「介護保険(かいごほけん)」、「年金制度(ねんきんせいど)」について、せつめいします。
そのまえに!保険のしくみについて、おはなししましょう。
保険ってどんなしくみになっているの?
とつぜんの出来事で生活に困っても、安心して暮らしつづけられるようにそなえておく「保険」。
じつは、この保険は「社会保障制度(しゃかいほしょうせいど)」の一つなんです。
社会保障制度には、つぎの4つの役割があります。
社会保険(しゃかいほけん)
人々が病気やけが、死亡、老齢、障がい、失業など、生活がこまったときに、お金やサービスなどを提供(ていきょう)する制度。国民みんなが入らなければなりません。
社会福祉(しゃかいふくし)
障がい者、母子家庭〔家族が母親だけのばあい〕・父子家庭〔家族が父親だけのばあい〕などの人たちが、安心して生活できるよう支援(しえん)を行う制度
公的扶助(こうてきふじょ)
生活に困っている人たちに、最低限度の生活を保障(ほしょう)して、自分の力で生活できるよう助ける制度
公衆衛生(こうしゅうえいせい)
人々が健康に生活できるように、病気などの予防などをおこなう制度
このような役割をもつ社会保障制度とは、私たちの生活には絶対にかかせません。
では、さきほどの「国民健康保険」と「介護保険」、「年金制度」は、どれにあてはまるでしょうか?
答えは「社会保険」です。
「社会保険」は、みんなが保険料(ほけんりょう)というお金をおさめることで、なりたっています。つまり、社会保険制度、すなわち社会保険とは、市民みんなで、ひとりひとりの生活をささえあう制度であると言えるでしょう。
つぎでは、いよいよこの3つについて、せつめいをしていきます。
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)ってなあに?
病気やけがをして、生活に困った人をたすける制度を、医療保険(いりょうほけん)といいます。
1961(昭和36)年から、日本では、公的(こうてき)な医療保険にはいることとなっています〔国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)〕。
この制度によって、病気やけがをしても、誰もが安心して病院などに行くことができるようになります。
そして、各地方の市役所であつかっている医療保険が「国民健康保険」です。
保険料は、世帯ごとに収入や資産額、世帯人数等におうじて決められています。
どのようなしくみなの?
病気(または、けが)をした!治療(ちりょう)するためには、お金がかかるし…。こまったなあ…
そんな場合に、
被保険者証(ひほけんしゃしょう〔保険がつかえることをしょうめいするもの〕)などをみせると、かかるお金を一部払うだけで、診察などをしてもらえます。
どれくらいお金をはらうの?
ふつうは、かかった費用の3割(原則)を払います
(たとえば、1,000えんかかったら、はらうお金は300えん、となります。)
小学校にはいるまえの子どもと、70さいいじょう・75さいみまんの人は2割、75歳以上は1割の負担になります。
ほかにも、長期入院や、病気をなおすために高いお金がかかるときにも・
1か月の医療費ではらわなければならないお金が、ルールで決められた金額(きんがく)をこえたばあい、そのこえた金額がはらいもどされる制度があります〔高額療養費の制度(こうがくりょうようひのせいど)〕。
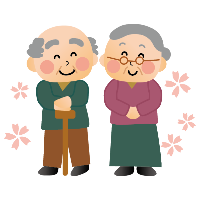
介護保険(かいごほけん)ってなあに?
歳(とし)をとってくると、体力のおとろえが原因で、病気にかかり、体が思うようにうごかなくなってしまったり、記憶する力がよわくなってきたりします。
そうなると、1人で生活することがむずかしく、お手伝いをしてくれる人が必要になると思います。そのお手伝いをすることを「介護(かいご)」といいます。
もし、じぶんや家族などが、介護が必要になったとき、自分ひとりの力でささえるのはむずかしいでしょう。
そこで!介護が必要な人、または介護をする人をサポートする制度が「介護保険」です。
介護が必要になったときでも、最期まで自分らしく暮らせるように、介護をする家族の経済・体力・心の負担を軽くし、みんなで支えあおうとする考え方です。
40歳以上の人たちみんなで保険料を払うことで、なりたっています。
「介護保険」の対象(たいしょう)となる人は、歳(とし)によって、次の2つに分けられています。サービスの利用内容や保険料のおさめ方などが、ちがいます。
65歳以上の人
寝たきりや、認知症(にんちしょう)などにより介護が必要、または、ふだんの生活に支援(しえん)が必要とみとめられたばあい
40歳から64歳までの人
末期(まっき)がん、関節(かんせつ)リユウマチなどの、歳(とし)をとることによってかかってしまう16種類の「特定疾病(とくていしっぺい)」により介護が必要になったばあい
どんなサービスを受けられるの?
サービスの内容は、「在宅(ざいたく)サービス」と「施設(しせつ)サービス」の2種類があります。
在宅サービス
家など自分が住んでいる場所でうけるサービス、または、家などから施設にかよって利用するサービスのこと。
たとえば・・・
- おふろにはいるのを手伝ってもらう。
- 食事を用意してもらう。
- 車いすなどをかしてもらう。
- 手すりをつけるなど、家での生活をたすける工夫〔住宅改修(じゅうたくかいしゅう)〕に必要なお金を一部出してもらう。
- いつも介護してくれる家族がいない日などに、そのあいだ一時的に施設で生活できる。
施設サービス
施設に入所して利用するサービスのこと。
利用者は、その施設で生活をしますが、まわりにはいつも介護をする人がいて、安心して過ごすことができます。
年金制度(ねんきんせいど)ってなあに?
世界でも、日本でも、お年寄りの長寿化(ちょうじゅか〔ながく生きること〕)がすすんでいます。
お年寄りになると、仕事ができなくなってくるので、生活に必要なお金がはいってきません。そのため、私たちは、自ぶんの親の老後を支えるため、また自ぶんの老後にもそなえるために、お金が必要になってきます。
そこでできたのが、市民ひとりひとりの老後をみんなでささえる制度が「年金制度」です。
自ぶん1人や、家族だけで老後を支えようとしても・・・
- 必要なぶんのお金がためられない
- お金をためるために、今の生活を必要以上にきりつめないといけない
- 家族や子どもを、たよりづらくなる
しかし!年金制度によって・・・
- そのときの経済や社会の状況におうじて給付〔お金をだして生活をたすける〕をうけられる。
- はばひろい年代の、たくさんの人でささえあうことで、効率(こうりつ)よくお金をあつめることができる。
このように、年金制度は、老後の生活に社会全体でそなえておくことで、一生安心して生活をすることを保障するために必要なものです。
どのようなしくみなの?
年金制度は、日本国内に住む20歳から60歳の全ての人が保険料を納め、その保険料を高齢者などへ年金として給付するしくみとなっています。
いま働いている世代〔現役世代〕がはらった保険料を、お年寄りなどへの年金としてつかうという「世代と世代の支え合い」という考え方〔賦課方式(ふかほうしき)〕で運営されています。
保険料のほかにも、年金積立金(ねんきんつみたてきん)や税金もつかわれています。
保険料のはらいかたは、職業(しょくぎょう)などによってちがいます。
自分のお店などをしている人など
毎月決まった金額の保険料を、自分で納めます。
会社員(かいしゃいん)や、公務員(こうむいん)など
毎月決められた計算で出された保険料を、はたらいている会社とで半分を負担します。保険料は毎月の給料から引かれます。
専業主婦(せんぎょうしゅふ)など
配偶者(はいぐうしゃ〔夫または妻〕)が、保険料をはらっているため、保険料をはらう必要はありません。
このようなしくみで、私たちは老後も生活に必要なお金をうけとることができるため、安心して暮らすことができるのです。
みなさんが安心して生活しつづけられるように、ひとりひとりが保険料をおさめることによって、生活を支えあう保険の制度。
そのしくみについて、理解(りかい)できたでしょうか?
社会保障の制度は、これだけではありません。もっともっと興味をもって、さらに学んでくださいね。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課秘書広報係
電話番号0997-22-1111(内線203・207)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ