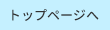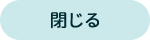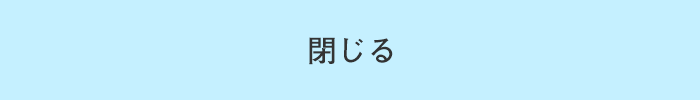後期高齢者医療保険
後期高齢者医療制度
少子高齢化にともない医療費が増大するなかで、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとして維持していくために、後期高齢者医療制度があります。
医療費は、全体の1割または2割(現役並み所得者は3割)を被保険者が自己負担します。残りの給付を行うための財源は、公費(国、県、市町村)から約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)から約4割、後期高齢者医療保険料から約1割となっており、高齢者世代と、現役世代が公平に負担をしながら、社会全体で支えあう仕組みになっています。
運営主体
この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行います。鹿児島県内の全市町村が加入する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)」は、平成19年3月1日に設立され、平成20年4月から運営されています。
ただし、資格確認書等の交付や医療費支給申請の受付、保険料の通知・徴収等の事務は市町村が行います。
【広域連合の役割】保険料の決定、医療の給付など
【市町村の役割】各種届出の受付、保険料の徴収、資格確認書等の交付など
届け出について
次のようなときは、届け出が必要です。以下の各手続きに必要なもの以外に、個人番号がわかるもの及び身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)等が必要です。
後期高齢者医療保険に加入するとき
後期高齢者医療保険に新たに加入された方に関しましては、被保険者証の廃止に伴い、「資格確認書」を申請によらず交付いたします。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 西之表市に転入してきたとき |
転出証明書、(県外からの転入の場合のみ)負担区分等証明書 |
| 75歳に到達したとき |
被保険者の振込口座がわかるもの |
| 生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止証明書 |
| 障害認定をうけるとき |
障害者手帳、被保険者の振込口座がわかるもの |
その他
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 住所・氏名・世帯主などが変わったとき |
資格確認書 |
| 世帯の合併、分離をしたとき |
資格確認書 |
| 死亡したとき |
資格確認書、喪主を務めた方の振込口座がわかるもの、喪主を務めたことがわかるもの(会葬のお礼状等)、相続人となる方の印鑑、振込口座がわかるもの |
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
令和6年12月2日から紙の保険証を廃止し、マイナンバーカードを保険証として使用していただく形になります。なお、現在お持ちの後期高齢者医療資格確認書に関しましては、券面に記載されている有効期限までは使用していただけるので、破棄することのないようご注意ください。(医療機関等のカードリーダーが何らかの理由で使用できない場合に、資格確認書の提示を求められる場合があります。)
また、すでにマイナンバーカードをお持ちの方で、保険証の利用登録がお済みでない方に関しましては、マイナポータルや医療機関等の窓口に設置している顔認証付きカードリーダー、市役所健康保険課国保年金係の窓口でも利用登録を行うことができます。詳しくは以下をご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
「マイナ保険証」篇 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp) (動画)
〇医療機関等を受診する際に利用できるもの
(以下、保険証利用登録しているマイナンバーカードを「マイナ保険証」と表記する。)
| マイナ保険証の有無 | 病院受診の際に使用できるもの |
|---|---|
|
マイナンバーカードの 保険証利用登録がお済みの方 |
・マイナ保険証 ・資格確認書(オンライン資格が見れない場合などに提示を求められることがあります) |
|
マイナンバーカードの 保険証利用登録がお済みでない方 または マイナンバーカードをお持ちでない方 |
・資格確認書 |
詳しくは、以下の鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページにてまとめてありますのでご参照ください。
マイナンバーカードの被保険者証としての利用について | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 (kagoshima-kouiki.jp)
マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証として利用登録されているものを指します。利用方法は、医療機関等の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を置いていただき、操作案内にしたがって診察時の受付を行います。
マイナ保険証で受診される際、顔認証や暗証番号での受付が難しい場合は、医療機関の職員による目視での本人確認を行うことができます。受付の際にご不明な点等あれば、医療機関の受付にいる職員にお声がけください。
マイナ保険証を使うメリット
マイナ保険証を使うメリットとしては、「過去の診療履歴やお薬情報を見れるようになり、より良い診療を受けることができる」、「救急現場でも過去の診療情報などが見れるので適切な応急処置等が行える」、「市役所窓口で行う高額療養費の手続きがなくても限度額を超える支払いが免除される」などといったものがあります。
マイナ保険証の利用登録・解除について
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録方法は、「ご自身のスマートフォンなどでマイナポータル にログインして登録する」、「医療機関等の窓口に設置してあるカードリーダーで受診前に登録を行う」等です。
ご自身での登録が難しい方は、市役所健康保険課国保年金係窓口にて利用登録を行うことができます。その際には、マイナンバーカードを作られた際にご自身で登録された4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)が必要になります。暗証番号を再設定したい場合には、市役所市民生活課の窓口にて、ご本人様に暗証番号の再登録をしていただきます。
マイナ保険証の利用が難しく、今後も利用する意向がない等の理由で保険証利用登録の解除を希望する場合は、市役所健康保険課国保年金係の窓口または郵送にて、保険証利用登録の解除申請ができます。解除申請受付後は「資格確認書」を申請によらず交付いたします。
また、保険証利用登録がお済みの状態で資格確認書の交付を希望する場合には、資格確認書の職権交付申請を市役所健康保険課国保年金係窓口で行っていただく必要があります。
マイナンバーカードを紛失等してしまった場合
マイナンバーカードを紛失等してしまった際には、マイナンバーカードの機能停止およびマイナンバーカードの再交付のお手続きが必要になります。つきましては、以下の連絡先にお問い合わせください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス:2番)
また、マイナンバーカードの再交付にはお時間がかかります。直ちに医療機関等に受診の必要がある場合には、資格確認書での受診をお願いいたします。(紛失された場合には市役所健康保険課国保年金係窓口にて再交付申請を行ってください。)
詳しくは、以下をご参照ください。
紛失・一時停止/セキュリティ| マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
資格確認書の交付について
資格確認書の紛失等により、再発行が必要となる方等に関しましては、窓口でのお手続きが必要となります。詳しくは以下をご参照ください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
|
資格確認書を紛失したり汚したとき |
・被保険者の名前がわかるもの ・代理人の身分証明書(代理の方が手続きを行う場合のみ) ・委任状(別世帯の代理の方が手続きを行う場合のみ) |
|
マイナ保険証の利用が難しく、 資格確認書の発行を希望する場合 |
・資格確認書 ・代理人の身分証明書(代理の方が手続きを行う場合のみ) ・委任状(別世帯の代理の方が手続きを行う場合のみ) |
委任状につきましては、下記リンクの鹿児島県後期高齢者医療広域連合が提供している「5 委任状」の様式を印刷のうえご準備いただくか、市役所健康保険課国保年金係窓口または郵送での受け取りも可能です。郵送等での受け取りを希望する場合には、市役所健康保険課国保年金係までお問い合わせください。
各種申請書様式 | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 (kagoshima-kouiki.jp)
医療機関等での受診の際に介助が必要な方へ
医療機関等を受診する際に、介助等が必要でマイナ保険証での受診が困難な方は、マイナ保険証を保有している場合でも、申請により「資格確認書」を取得することが可能です。福祉施設の利用者や在宅の要介護者につきましても、代理申請によって令和8年8月以降の年次更新でも「資格確認書」の交付を継続することができます。
よくある質問
Q1.マイナ保険証の利用登録をしているかがわからない場合はどこで確認できるか。
A1.利用登録状況は、マイナポータル で確認することができます。また、医療機関等の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダーや市役所健康保険課国保年金係窓口でも登録することが可能です。
ログインをする際にはマイナンバーカードを作られた際にご自身で登録された4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)が必要になります。
Q2.「資格確認書」とは何か。
A2.「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない方などに交付する紙のカードになります。使用方法は保険証と同様に、医療機関等を受診される際に提示していただくものになります。
Q3.マイナ保険証は持っているが、被保険者本人が寝たきり状態等で使用するのが難しい場合はどうすればよいか。
A3.すでにマイナ保険証をお持ちの方は、「保険証としての利用登録を解除した」もしくは「電子証明書の有効期限が切れた」等の状況になるまでは、マイナ保険証を保持していることになります。
もし、マイナ保険証による受診が難しく、暫定運用期間も引き続き資格確認書の利用を希望する場合には、資格確認書の継続交付申請が必要になりますので、市役所健康保険課国保年金係窓口までお問い合わせください。
Q4.マイナ保険証を持っていないと医療費は10割負担になるのか。
A4.マイナ保険証をお持ちでない方は、現在交付されている資格確認書を有効期限まで使うことができます。
Q5.今まで交付されていた「限度額適用認定証」「限度額適用標準負担額減額認定証」はどうなるのか。
A6.令和7年8月1日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用標準負担額減額認定証」の発行はできません。ただし、申請により自己負担限度額の区分を併記した「資格確認書」を発行することが可能です。医療機関等を受診される際には、区分を併記した資格確認書を提示していただくことで、月ごとの保険診療分の支払いが自己負担限度額までになります。(前年度までに認定証の交付申請を行っている方は、現在交付している資格確認書に併記されているため、申請は不要です。)
また、マイナ保険証で受診される場合は、交付申請を行っていない方でも、マイナ保険証の提示だけで自己負担限度額までのお支払いになります。
はり・きゅう施術料の助成について
一定の要件を満たす国保・後期被保険者が指定施術所ではり・きゅうの施術を受けるとき、はり・きゅう受領者証を提示することによって1回につき600円の施術料の助成が受けられます。
手続きに必要なもの
・療養を受ける方の資格確認書及び印鑑(認め印可)
・申請に来る方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
注意事項
・後期保険料を滞納している被保険者の方には、受領者証を交付できません。
人間ドック・脳ドックの利用補助について
生活習慣病や疾病の早期発見・健康増進を目的として「1日・2日人間ドック」、「脳ドック」の施設利用者に対する助成を行っています。
助成額
・人間ドック 25,000円(1日・2日ともに同額)
・脳ドック 20,000円
申請方法
1.医療機関に予約をする。
2.下記の「申請に必要なもの」を持って、健康保険課国保年金係の窓口で手続きを行う。
3.医療機関で受検する際、2.の手続きでもらう施設利用券を提出する。
※受検後、医療機関から届く結果と長寿健診の受診券を持って、健康保険課国保年金係の窓口までお越しください。
申請に必要なもの
・人間ドックまたは脳ドックを受検する方の資格確認書及び印鑑(認め印可)
・申請に来る方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
注意事項
・受検する前に申請を行わないと助成できませんので、必ず事前に手続きをお願いします。
・後期保険料を滞納している被保険者の方には助成できません。
・人間ドック・脳ドックのいずれか、年度1回を限度とします。
・年度内に集団健診か個別健診を受診される方については助成ができません。
問い合わせ先
【保険料率・制度全般について】鹿児島県後期高齢者医療広域連合 電話099-206-1397
【各種届出について】健康保険課 国保年金係 電話0997-22-1111(内線311・312)
【保険料額・納付方法・口座振替について】税務課 市税係 電話0997-22-1111(内線229・233)
【納付相談について】税務課 収納整理係 電話0997-22-1111(内線231・232)
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号(自治会館2階)
ホームページ:http://www.kagoshima-kouiki.jp/
電話:099-206-1397(代表)
ファックス:099-206-1395
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ