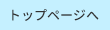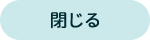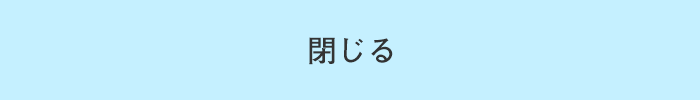介護サービスを受けるには
介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
申請する

申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は、本人のほか家族でもできます。
また、次のところにも申請の依頼ができます。(更新申請も含む)
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
申請に必要なもの
申請書・・・高齢者支援課介護保険係の窓口に置いてあります。
介護保険の保険証・・・40~64歳の方は健康保険の保険証
マイナンバーカード
申請書には、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。
かかりつけの医師を、確認しておきましょう。
要介護認定
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査
市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医の意見書
市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
市町村が取り寄せますので、本人が提出する必要はありません。
主治医がいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
軽度の介護が必要な方は、状態の維持または改善がどのくらい可能かを重点的に審査されます。
結果の通知
審査の結果は、申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
認定結果を確認しましょう
介護認定審査会の審査結果によって、あなたに必要な介護(支援)の度合いが認定され、市町村から認定結果が通知されます。認定結果通知書と保険証の記載を確認しましょう。
認定結果通知書に記載されていること
- あなたの要介護状態区分
- 認定理由
- 認定の有効期限など
保険証に記載されていること
- あなたの要介護状態区分
- 認定の有効期限
- 介護認定審査会の意見
- 支給限度額など
介護保険の支給限度額
介護保険サービスを利用する際には、要介護状態区別に保険から給付される上限度額(支給限度額)が決められています。利用者は原則としてサービスにかかった費用の1~3割を自己負担します。
認定結果に納得できないときは?
要介護認定の結果に疑問や不服がある場合、まずは、市町村の窓口までご相談ください。それでも納得できない場合には、60日以内に、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
・ 再審査の結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用します。
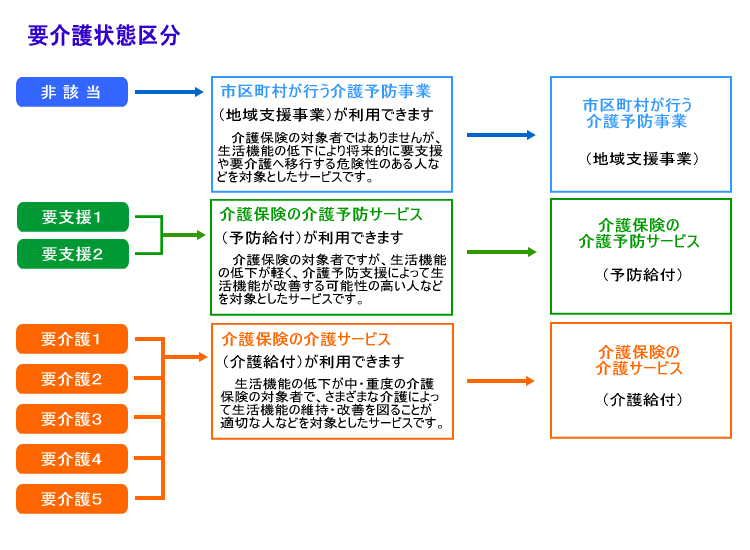
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ