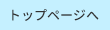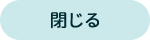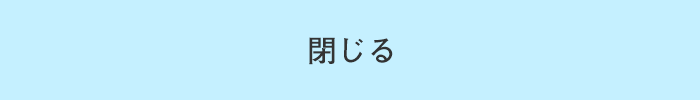国民健康保険税
国民健康保険税(以下、「国保税」という)は、国民健康保険事業の運営(財源)に充てるための目的税です。
国保税の「納税義務者」は世帯主です
国保世帯では、世帯主が「納税義務者」となりますので、各種通知は世帯主宛に行います。
国保加入者でない世帯主(擬制世帯主という)の場合、国保税の課税内容にその世帯主は含まれませんが、納税義務者として納税の義務は生じます。
国保税の算定方法
国保税の算定方法は、西之表市国民健康保険税条例により規定されており、それぞれの世帯の加入者数、年齢及び所得等を基に、毎年度7月に年税額の本算定を行います。
国保税は、所得割、均等割及び平等割の3項目からなる基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金課税額(支援分)の合計額からなり、さらに40歳~64歳の方については介護納付金課税額(介護分)が加算されます。
なお、それぞれの課税額には課税限度額が設けられています。
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
|
基礎課税額 (医療分) |
7.1% | 20,500円 | 19,000円 |
660,000円 |
|
後期高齢者支援金課税額 (支援分) |
3.2% | 8,500円 | 7,000円 | 260,000円 |
|
介護納付金課税額 (介護分) |
2.1% | 8,000円 | 6,500円 |
170,000円 |
1.所得割は、世帯における国保加入者の前年中の総所得金額を基に計算されます。
所得割額=(前年中の総所得金額-43万円)×税率
2.均等割は、世帯の国保加入者数を基に計算されます。
均等割額=国保加入者数×定額
3.平等割は、1世帯あたりで計算されます。
平等割額=1世帯×定額
国民健康保険税の納付方法と納期限
1.納付書「普通徴収」
市役所から納税通知書とともに送付される納付書を使用し、金融機関、コンビニエンスストア、アプリ決裁サービスで納付をお願いします。
期別の納期限は、下記のとおりです。
|
期別 |
納期限 |
|---|---|
|
第1期 |
令和7年7月31日(木曜日) |
|
第2期 |
令和7年9月1日(月曜日) |
|
第3期 |
令和7年9月30日(火曜日) |
|
第4期 |
令和7年10月31日(金曜日) |
|
第5期 |
令和7年12月1日(月曜日) |
|
第6期 |
令和7年12月25日(木曜日) |
|
第7期 |
令和8年2月2日(月曜日) |
|
第8期 |
令和8年3月2日(月曜日) |
2.口座振替「普通徴収」
金融機関での届出により、納付書から口座振替に変更することができます。
口座振替は、各納期限に、指定口座から引き落としを行います。
3.年金天引き「特別徴収」
一定条件を満たす世帯については、偶数月に支給される年金からの天引き(特別徴収)を行います。
※申出により、年金天引きから口座振替に変更することができます。
なお、4月・6月・8月の特別徴収については、原則、前年度2月の特別徴収額と同額で「仮徴収」を行い、7月の本算定を受けて、10月・12月・2月で年税額の調整を行います。
|
期別 |
実施日 |
|---|---|
|
第1期 |
4月の年金支給日 |
|
第2期 |
6月の年金支給日 |
|
第3期 |
8月の年金支給日 |
|
第4期 |
10月の年金支給日 |
|
第5期 |
12月の年金支給日 |
|
第6期 |
2月の年金支給日 |
[軽減]所得による軽減判定【申請不要】
世帯における前年中の総所得金額等が一定基準以下の場合、国保税のうち均等割額と平等割額を軽減します。この軽減判定には、国保加入者でない世帯主(擬制世帯主)の総所得金額も含みます。
また、65歳以上の年金受給者の場合、年金所得から15万円を控除し、軽減判定を行います。
|
軽減となる世帯の総所得金額等 |
軽減割合 |
|---|---|
|
430,000円+(560,000円×国保加入者数【※1】)+100,000円×(給与所得者等の数【※2】-1)以下 |
2割軽減 |
|
430,000円+(305,000円×国保加入者数【※1】)+100,000円×(給与所得者等の数【※2】-1)以下 |
5割軽減 |
|
430,000円+100,000円×(給与所得者等の数【※2】-1)以下 |
7割軽減 |
※1 国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保検者に移行した者を含む
※2 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
所得申告がない場合、軽減判定をすることができません
軽減判定には、世帯全員の所得申告が必要となります。1人でも所得申告をしていない方(未申告者)がいる場合、軽減判定を行うことができません。前年中に所得が無かった方も申告は必要ですので、忘れずに申告しましょう。
[免除]産前産後期間の免除【申請必要】
対象者
西之表市の国民健康保険に加入している人で令和5年11月以降に出産予定、出産した人
免除額
令和6年1月1日以降の対象となる期間の所得割額と均等割額の全額(月割にて免除)
免除期間
出産予定日又は出産日の属する月の1か月前から出産予定日(出産日)の翌々月までの4か月相当分を免除
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から出産予定日(出産日)の翌々月までの6か月相当分を免除
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます)
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 1か月後 | 2か月後 | ||
| 単胎の方 | ※出産予定月 | |||||
| 多胎の方 | ※出産予定月 |
※届出が出産後の場合は「出産月」
必要書類
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書(健康保険課備付)
2.出産予定日と出産する人が確認できる書類
3.単胎妊娠又は多胎妊娠を確認できる書類
1~3をご準備の上、健康保険課に申請してください。
(注)2、3以外の書類の提出が必要になる場合があります。
※出産予定日の6か月前から申請できます。
[軽減]未就学児への均等割軽減について【申請不要】
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割保険税を軽減します。
| 軽減割合 | 軽減後の割合 | 軽減後の均等割保険税 |
|---|---|---|
| 軽減なし | 5割軽減 | 14,500円 |
| 2割軽減 | 6割軽減 | 11,600円 |
| 5割軽減 | 7.5割軽減 | 7,250円 |
| 7割軽減 | 8.5割軽減 | 4,350円 |
[軽減]非自発的失業者の軽減申請【申請必要】
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された雇用保険受給資格者証をお持ちの方が次の条件をすべて満たす場合、申請により一定の期間、国保税が軽減されます。
軽減の対象条件
- 離職日に65歳未満であること(離職時点の年齢が満64歳以下)
- 短期的・季節的雇用者でないこと
- 雇用保険受給資格者証の離職番号が下表の数字であること
|
離職番号 |
離職理由 |
|---|---|
|
11 |
解雇 |
|
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
|
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
|
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
|
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
|
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
|
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
|
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
|
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※雇用保険の特例受給資格者及び高齢受給資格者は対象となりません。
軽減内容
対象者の前年給与所得を30%とみなし、所得割を計算します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
注意事項
・ 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
・ 申請が遅れても、さかのぼって軽減を受けることができます。
・ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
[減免]旧被扶養者に対する減免措置【申請必要】
被用者保険(職場の健康保険等)に加入していた方が75歳の誕生日を迎えたことにより後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者だった方は、国民健康保険に加入することになります。それに伴い国民健康保険税が新たに賦課されることで、負担が増加します。この負担を軽減するため、以下の条件に該当する方は減免措置を受けることができます。
対象者
・ 国保の資格を取得した時点で、65歳以上であること。
・ 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
・ 国保の資格を取得した日に、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入していること。
減免措置の内容
・ 所得割額は、全額を免除します。
・ 均等割額は、1/2を減免します(7割・5割軽減世帯は除く)。
・ 平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、1/2を減免します(7割・5割軽減世帯は除く)。
※均等割及び平等割の減免期間は最長24か月間です。
減免措置の手続き
◇西之表市在住で旧被扶養者となった方
被用者保険の保険者が発行した、「資格喪失証明書」(被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)を健康保険課国保年金係に提出してください。
◇前住所在住時に旧被扶養者となった方
西之表市での国民健康保険資格取得の手続きをする際、前住所の市区町村で発行した「旧被扶養者異動連絡票」を健康保険課国保年金係に提出してください。
※西之表市から転出される方には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行しますので、転出先の市区町村に提出してください。
[減免]災害や収入減等による減免申請【申請必要】
申請により、災害や離職等(自己都合退職・定年退職を除く)による収入減等が認められた場合、基準の範囲内で減免を行います。対象となる国保税の減免は、原則納期限までに申請があった納期未到来分に限られます。
※前納していても納期未到来であれば対象です。
ただし、減免決定を受けた場合でも、その後資力の回復等により減免が不適当と認められた場合には、減免を取消します。
国民健康保険の資格(取得・喪失等)に関する手続き
健康保険課のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ