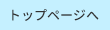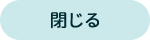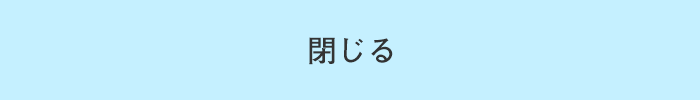避難指示等発令情報(避難情報)について
津波、火災、倒壊や崩壊などの危険が予測されるときや実際に迫っているときには「避難」が必要です。
単純に地震の大揺れがきたから「避難しないとだ!」というのは、正しくありませんが、家が崩れるかもしれない、がけ崩れがおこるかもしれないなどの心配があれば早めの避難が必要となります。
市が発令する避難情報等について
市は、各種災害等が発生するおそれが高い場合に市民の皆様へ避難情報を発令します。
情報の種類によって、避難行動などに違いがありますのでご確認ください。
避難情報の種類と状況、市民の動き
1.自らの避難行動を確認(警戒レベル1・2)
(発表される状況)
気象状況等の情報発信により、災害に対して注意喚起
今後気象状況悪化のおそれ(レベル1)、気象状況悪化(レベル2)
早期注意情報(レベル1)、大雨・洪水・高潮注意報等(レベル2)
(市民の動き)
防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高めてください。
ハザードマップなどにより自宅・施設等の災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認するなど、避難に備え自らの避難行動を確認してください。
2.「高齢者等避難」の発令(警戒レベル3)
★ 危険な場所から高齢者等は避難 ★
(発表される状況)
危険な場所(土砂災害警戒区域等)から高齢者など要配慮者、特に避難行動に時間を要する者が、避難行動(立退き避難)を開始するべき段階
災害のおそれあり
(市民の動き)
避難要配慮者(高齢者や乳幼児のいる世帯など避難に時間がかかる方)は避難行動を開始します。その他の市民は家族との連絡、非常用持出品を用意し、避難準備を行います。
また、早めの避難が望ましい場所の住民等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。
3.「避難指示」の発令(警戒レベル4)
★ 危険な場所から全員避難 ★
(発表される状況)
居住者等は危険な場所(土砂災害警戒区域等)から全員避難する必要がある
災害のおそれ高い
土砂災害警戒情報、津波注意報・警報等を参考
(市民の動き)
居住者等は危険な場所から全員避難する必要があります。
具体的にとるべき避難行動は「立退き避難」を基本とするが、洪水等及び高潮に対しては屋内で安全を確保できるか等を確認できる場合、「屋内安全確保」することも可能です。
※令和3年5月20日の災害対策基本法の改正により「避難勧告」は廃止されました。
4.「緊急安全確保」の発令(警戒レベル5)
★ 命の危険 直ちに安全確保! ★
(発表される状況)
災害が発生又は切迫している状況。即ち居住者等が身の安全を確保するために立退き避難することが、かえって危険であると考えられる状況
指定緊急避難場所等への「立退き避難」を中心とした避難行動から、「緊急安全確保」を中心とした行動へ、行動変容する必要がある
災害発生又は切迫 (※必ず発令される情報ではない)
(市民の動き)
居住者等は命の危険があることから、直ちに安全確保する必要があります。
※本来は「立退き避難」をすべきであったが、避難し遅れた居住者等がとる次善の行動であるため、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。早めの避難を心がけましょう。
気象庁ホームページ「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」
避難行動
- 個々の家屋の倒壊やがけ崩れなど、個々の立場で危険を判断して避難しなければならない場合があります。どこへ避難するかはそのときの判断や、市や消防、警察などの指示によります。
- ある範囲(区域)や場所の住民が危険に遭うことが予想される場合には「避難指示等」が出されます。また、市全域に「避難指示等」を発令することがあります。しかし、きわめて短時間のうちに危険が発生したような場合には、地域の判断で全体が緊急の行動を起こす必要があります。
- 避難は、弱者(高齢者、障害のある人、病弱な人、乳幼児など)が最優先されなければなりません。
- 大雨や暴風のなか、海岸近くや夜間など、避難することがかえって危険となる場合があります。余裕を持った避難行動を心がけましょう。
避難のルール
- 足と頭の保護を。
- 外出中の家族に連絡メモを。
- 非常持ち出し品以外に、むやみに荷物を持たない。
- 避難場所へ移動するときは、狭い道や看板の下などは避ける。
- 避難は徒歩で。
- 近所の人達と集団で、指定された場所へ。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課防災消防係
電話番号0997-22-1111(内線 205)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ